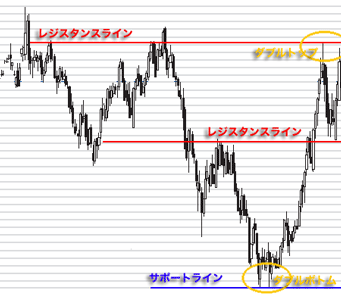テクニカル分析について
ここでは、一般的にな有名な法則であるダウ理論について説明します。
ダウ理論とは、チャールズ・ダウが19世紀末頃に「ウォール・ストリート・ジャーナル」で執筆していたもので、市場の平均値は需給に影響する全ての要因を反映すると発表しダウ11種平均を掲載しました。
ダウ理論では、まずアップトレンドとダウントレンドを定義します。山と谷の繰り返しで上昇を構成するのがアップトレンドで、山と谷の繰り返しで下降を構成するのがダウントレンドです。またダウは投資家にとって最も重要なのは市場の方向性であるとし、トレンドをメイントレンド、マイナートレンド、小トレンドの3種類に大きく分類します。その中で1番重視されるのがメイントレンドで通常1年以上、時には数年間継続し、マイナートレンドはメイントレンドの調整局面とみなされ通常数週間から数ヶ月継続します。その他重要な要素として、出来高をあげています。出来高は長期トレンドの方向に従い増減するという法則で、メイントレンドが上昇基調であれば出来高は価格が上昇するに連れて増加し、下落時には減少するとします。
現在、テクニカル分析とされているものの多くは、このダウ理論に影響を受けており、ダウ理論はテクニカル分析の定石とも言えます。これらテクニカル分析に対する批判としては、ランダムウォーク理論があります。これは、過去の変化はおのおの独立したものと考え、過去の値動きは将来の価格の方向を占うに際し信頼すべき指標ではないと考えるものです。
ここでテクニカル分析の一例を説明したいと思います。
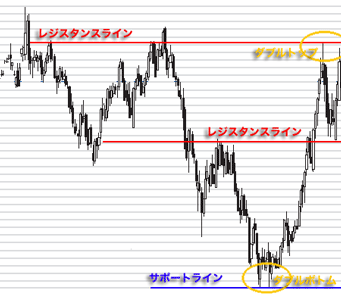
図中のチャートでは一度、天井を付けた後下落トレンドが続いていましたが、ある一定の値付近でサポートされ、ダブルボトムを形成するとその後は、上昇トレンドとなっています。暫く上昇トレンドが続いていましたが、途中売り圧力を受け、一定値を抜け切れていません。その値(レジスタンスライン)は過去の高値とも一致しており幾度も抵抗を受ける強力な抵抗帯ともいえます。それから高値がダブルトップを形成した可能性があり、今後は下落トレンドに向かうかもしれません。その場合は、以前のレジスタンスラインである値が、サポートラインとして機能する可能性があるためその値付近まで下落する可能性があると分析したりします。
テクニカル分析では、安値と安値または高値と高値を結んだトレンドラインやサポートライン(支持線)、レジスタンスライン(抵抗線)などの補助線を引いて分析します。また、ダブルトップ、ダブルボトムなどのチャートパターンから今後の価格推移を推測することもあります。
テクニカル分析の中では、現在のトレンドを判断することを目的としたチャート、 例えば移動平均、エリオット波動、ポイント・アンド・フィギュア、パラボリック、 新値足等のトレンド系チャートと相場の振れ具合(振幅)を見ていく手法、例えば ストキャスティックス、RSI、MACD等のオシレーター系チャートに大きく分ける ことができます。
| 系統 | 価格分析 | 価格以外の分析 |
| トレンド系 | 移動平均 | OBV(On Balance Volume) |
|---|
| エリオット波動 | - |
| パラボリックポイント・アンド・フィギュア | - |
| 新値足 | - |
| オシレーター系 | ストキャスティックス | ボリュームレシオ(VR) |
|---|
| ウィリアムズ%R | - |
| RSI | - |
| MACD | - |
| DMI | - |
| その他 | 一目均衡表 | ギャン理論 |
|---|